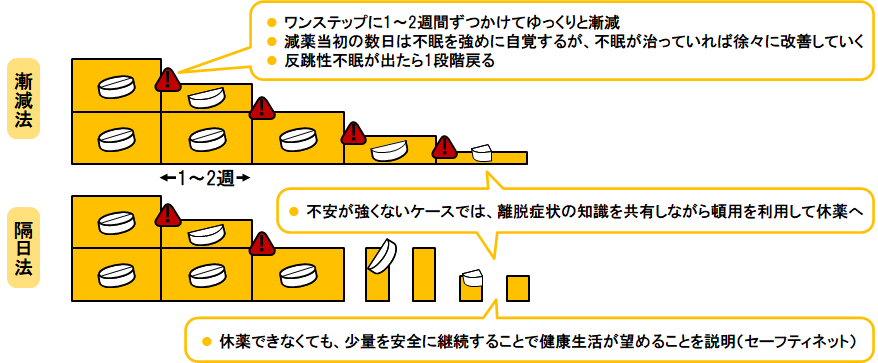不眠症治療アルゴリズム
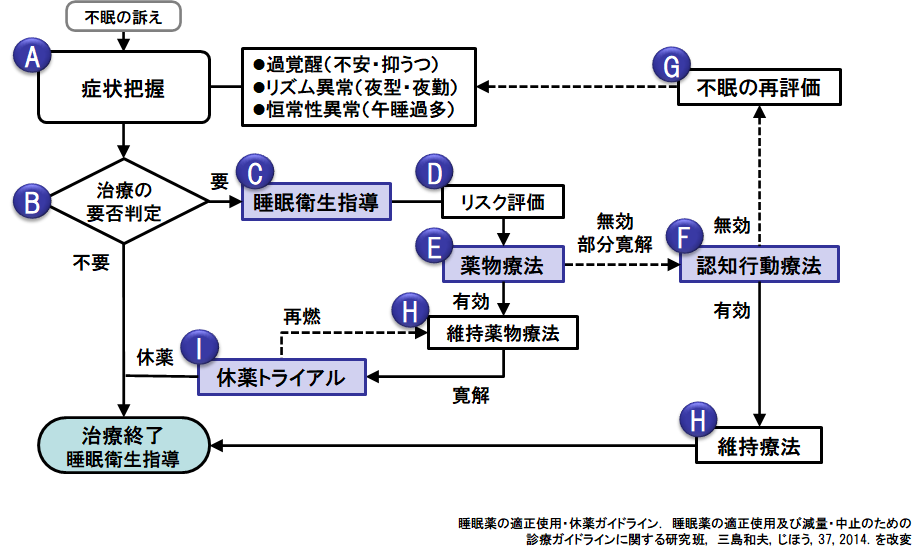
睡眠衛生のための指導内容
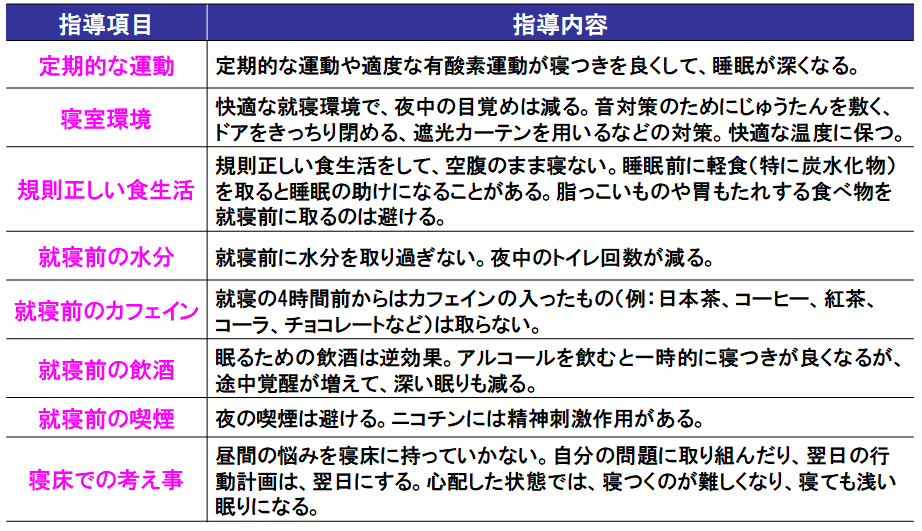
睡眠薬投与計画の重要性
有効性評価には一定の投与維持期間が必要
- 短期間での増量・加剤は依存の可能性を高める
治療のゴールを設定する
- 睡眠困難と日中の機能障害、両者の改善(寛解)が得られ、一定期間が過ぎたら、減量・休薬の検討
投与期間中は病状及び薬効をモニタリング&再評価
- 長期服用は依存のリスクを高める
多剤併用を考える前に
総就床時間・生活の再チェック
- 眠くないのに就床
- 不適切に長い総就床時間
診断を再度見直す
薬物選択の再考
- 不眠のタイプに作用時間が合っているか
認知行動療法的アプローチの応用
- 実際に眠ることのできる時刻を考慮し、服薬時刻、就床時刻を遅くする
- 起床時刻を早めて総就床時間を短く適正化
- 少しでも眠ろうと長く寝床の中で過ごすことが不眠の原因
- 寝床で睡眠以外(読書やテレビ鑑賞)はしない
- 夜中に目覚めたら別室へ
- 寝床以外(ソファーなど)では睡眠しない
- 眠くなったら寝床へ
減量・休薬法
現在服用中の薬剤数・薬剤投与量を徐々に減量
- ゆっくりと慎重に半年くらい時間をかけながら減量・中止
睡眠習慣の適正化と平行して行う
- 就床時刻適正化、総就床時間短縮適正化
急な減薬・休薬に注意
- 反張性不眠、動悸、不安感等を引き起こすことがある
- 休薬は十分減量してから
- 心理的サポートは全ての段階で必要
休薬日を設定する場合には、眠くなってから寝床につくか、1時間就床時刻を遅らせる
急な中断による離脱症状を避けるために、睡眠薬の減量・中断では、漸減法や隔日法といった方法が用いられます。